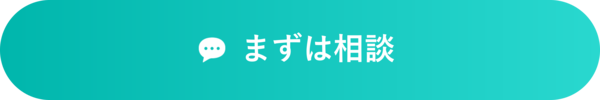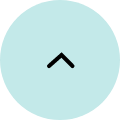<国際ロボット展インタビュー>実行委員長 稲葉 清典 氏(ファナック専務執行役員 ロボット事業本部長)

あらゆる産業で期待が高まるロボット技術。一昔前とは比較にならないほどタクトタイムが短縮し、安全性や使いやすさは向上している。国際ロボット展(iREX)実行委員長であり最大ブースを確保する出展社でもあるファナックの稲葉清典氏に同展の見どころと期待を聞いた。
来場者とともに未来を描く場に
——海外出展も増え、今回のiREXは過去最大規模となります。会場で期待することは。
「国内外からジャンルを問わず多くのロボットおよび関連機器等が出展します。出展者数は海外を含め約650。コロナ禍の制限がない中での開催は2019年以来で、その時の来場者数が約14万人だったので、今回は同等かそれ以上が来場されるということを踏まえて準備してきました。展示会は重要な新技術や新商品の発信の場であるので、活発な商談の場になります。産学連携やオープンイノベーションの場となることも期待しています」
——開催テーマを「ロボティクスがもたらす持続可能な社会」とされました。この狙いや意図は。
「日本ロボット工業会が創立50周年を迎えた昨年、『ロボティクスがもたらす持続可能な社会』をテーマにいろいろなイベント、周年事業を実施しました。今回のiREXの運営・実行委員会において、本テーマが同展のテーマに1番ふさわしいと考え採用しました。日本が抱える様々な社会問題解決に対して、政府からのロボット技術への強い期待もあります。一方で、国連がSDGsとして掲げている各開発目標に対してもロボット技術が直接・間接的に貢献できると、国際ロボット連盟(IFR)が発表しています」
——いち押しの企画や見どころを教えてください。
「最初に挙げたいのはもちろん、各ロボットメーカーのブースです。新たなロボット活用の姿が示されると確信しているのでぜひ見ていただければと思います。また自動化のソリューションという観点からはシステムインテグレーターや商社、デバイスメーカーの展示も同様に見応えがあると思います。注目企画としては2つあり、1つはサスティナブル・共存・協働をコンセプトとした主催者の企画エリア『見て!触れて!想像しよう!ロボティクスがもたらす持続可能な社会』。ロボットメーカーを中心とした、参加・体験型の催しです。もう1つは日本科学未来館とのコラボ企画『出張!未来館!新ロボット展示を体験!』で、同館が11月にリニューアルするのに合わせてロボットに関する新常設展示が特別にiREXに出張します。いずれも来場者とともに未来を描き想像する企画です」
信頼性+使いやすさ
——実行委員長であると同時に貴社は有力出展社でもあります。出展社としてのアピールもお願いします。
「ファナックのロボット出荷は累計100万台を達成しました。最初の50万台までに40年を要しましたが、残りの50万台は6年で達成しています。日本を含め世界中で自動化の需要が強くなっています。展示会では、どのようなお客様がいらっしゃったとしても、『これ、うちに使えそうだな』と言っていただけるような、現場での活用を連想できる展示をします。ブース全体が『アプリケーションモール』。パレ・デパレタイジング、ピッキング、組立、ロボット加工、EV用バッテリーの適用など、幅広い用途での適用を用意しています。ロボットの供給だけでなく、その使い方までをお客様と連携することを重視しています。併せて、それぞれの分野に精通し独自のソリューションをもつシステムインテグレーター、商社、装置メーカーなどの方々と連携をしながら、自動化の普及に努めたいと思います」
——貴社の強みは。
「『使いやすさのファナック』を見ていただけたら嬉しい。直近の5年間は使いやすさを採り入れながら、開発基本方針である信頼性との両立に努めています。産業用ロボットには使いやすさという概念があまりありませんでしたから。その代表格が初めての方でも簡単に使える協働ロボットCRXです。直感操作、簡単設置、メンテナンスフリーを実際に触って感じていただきたいです。またAIやセンシング技術を用いることで、調整ノウハウ、調整時間、周辺機器などを削減することができます。使用されている要素技術は高度になってきていますが、逆にその技術はロボットを『使いやすく』することに貢献しています」
(提供:日本物流新聞社)