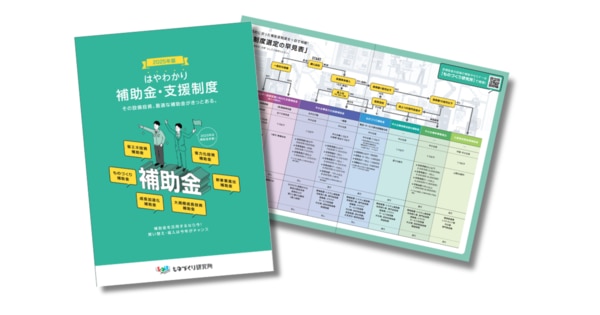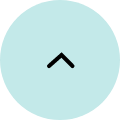【2025.3月】製造業必見!省エネ補助金・省力化投資補助金の採択ポイント
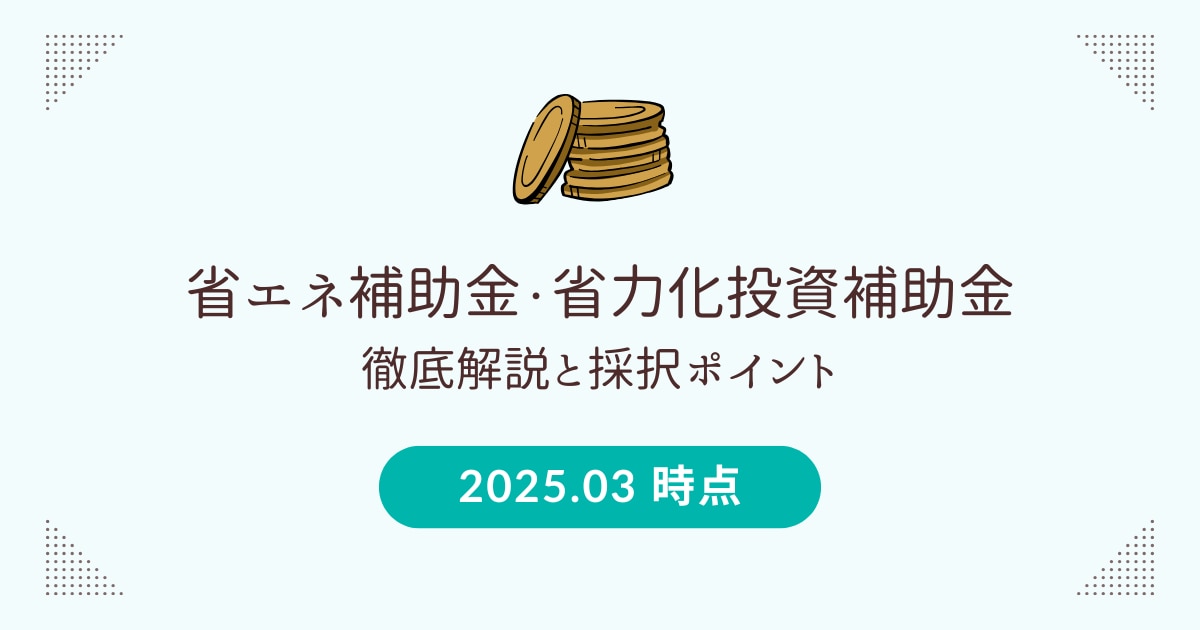
2025年度、製造業向けに過去最大規模の予算が投入された省エネ補助金 設備単位型(以下、省エネ補助金) と省力化投資補助金 一般型 (以下、省力化投資補助金) について解説していきます。
これらは設備更新や生産性向上を目指す企業にとって、大きな投資機会となっています。
本年の製造業向け補助金は、DX推進や省エネ・省力化を強く意識した傾向が見受けられます。
また申請要件の明確化と採択基準の透明性が高まり、過去の採択事例から効果的な申請戦略が見えてきました。
省エネ補助金では省エネ率の計算方法が、省力化補助金では賃上げ要件が採択の鍵となります。これらのポイントを押さえた準備が成功への近道です。
本記事では、工作機械などへの設備投資に活用できるこれらの補助金について、申請から採択までのプロセスと成功のポイントを解説します。複雑な申請要件も、正しい知識があれば効果的に活用できる有効なツールです。
この記事の目次[非表示]
省エネ補助金(設備単位型)の申請方法と採択されるためのポイント
省エネ補助金(設備単位型)とは?
省エネ補助金は、省エネ性能の高い設備への更新を支援する制度です。
既存設備を省エネ性能の高い新しい設備に入れ替える際に、設備本体代の3分の1が補助されます。
特筆すべき点として、リース契約での活用も可能であることや、申請から採択までの期間が比較的短いことが挙げられます。
「ユーティリティ設備」と「生産設備」の2つのカテゴリーがあり、空調やコンプレッサーといったユーティリティ設備だけでなく、工作機械などの生産設備も対象になります。
特に製造業では、マシニングセンタや旋盤などの工作機械の更新に活用するケースが多く見られます。
「うちの古い設備を入れ替えたいけど、予算が…」と悩んでいる方には、この補助金がぴったりかもしれません。
省エネ補助金(設備単位型)の申請に必要な要件を解説
省エネ補助金を申請するには、主に「省エネ要件」と「計画要件」の2つを満たす必要があります。
省エネ要件には以下の3つがあり、どれか1つを満たせば申請可能です
- 省エネ率要件:設備更新により10%以上の省エネ効果を達成すること
- 省エネ量要件:設備更新により原油換算で1キロリットル以上のエネルギー削減を実現すること
- 費用対効果要件:1000万円の投資あたり原油換算で1キロリットル以上の省エネ効果を得ること
実際には、一般的な工作機械の更新では省エネ率要件(10%以上)を満たすことを目指すのが現実的です。
過去の採択事例を見ると、マシニングセンタや旋盤などの設備更新では、だいたい20%くらいの省エネ率が採択のボーダーになると考えられています。
各設備種類によって採択ラインは異なるので、過去の採択事例を参考にすることをお勧めします。
また「計画要件」では、今後数年間で社内の省エネをどのように進めていくのかを示す計画書の作成が必要です。
現時点では詳細なフォーマットは公開されていませんが、あまり複雑な内容は求められないと予想されています。
省エネ率計算方法のコツと高採択率を実現するテクニック
省エネ率を計算する方法には「指定計算」と「独自計算」の2つがあります。採択率を高めるためには、この選択が重要なポイントとなります。
「指定計算」はメーカーが登録済みの省エネ率をそのまま使用する方法です。
手続きは簡単ですが、比較対象が1台前のモデルとなるため、高い省エネ率が出にくいという欠点があります。
一方「独自計算」は、現在使用中の設備を実測し、導入予定設備と比較する方法です。
手間はかかりますが、実際の使用状況との比較になるため、より高い省エネ率を示せる可能性が高まります。
採択を確実にしたい場合は「独自計算」の活用が効果的です。
特に10年以上使用している古い設備からの更新では、より高い省エネ率が算出できる可能性があります。
省エネ補助金(設備単位型)の申請スケジュールと準備のタイミング

2025年度の省エネ補助金申請スケジュールは次のように見込まれています。
- 一次締切:4月下旬
- 一次採択発表:6月下旬
- 二次締切:6月末
- 二次採択発表:8月上旬
この補助金は採択以降に交付決定になりますので採択されたタイミングで発注いただいて問題ありません。
事業完了期限は原則として翌年1月31日ですが、納期が間に合わない場合は「複数年度申請」で1年延長できます。
この補助金の魅力の一つは、実績報告から補助金入金までの期間が短いことです。
最短のケースでは、年内に設備を導入し、翌年1月までに支払いを完了させれば、3月末には補助金を受け取ることができます。
資金繰りの面でもメリットがある制度設計となっています。
また「いつから準備を始めればいいですか?」という質問をよく受けますが、申請締切の1〜2ヶ月前から本格的な準備を始めるのが理想的です。特に独自計算を行う場合は、設備の実測や計算書の作成に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが採択率向上につながります。
省力化投資補助金(一般型)の採択されるためのポイント
省力化投資補助金(一般型)とは?
省力化投資補助金は、工数削減や工程集約、自動化といった省力化・省人化を目的とした設備投資を支援する制度です。
中小・中堅企業を対象としており、規模に応じて最大1億円までの補助金を受けることができます。
この補助金の大きな特徴は、カスタマイズ機器だけでなく汎用設備も対象になることです。
多様な加工ができる最新工作機械や自動取出し機能を持つ設備など、生産性向上に寄与する様々な設備が対象となり得ます。
製造業にとっての最大のメリットは、単なる設備更新だけでなく、生産プロセス全体の効率化を図れることです。
特に人手不足に悩む製造現場では、自動化・省力化のための投資は将来の競争力強化につながります。
省力化投資補助金(一般型)の賃上げ要件と対応策
省力化投資補助金の最大の特徴は「賃上げ要件」にあります。
具体的には次の3つの要件があります
- 給与支給総額の増加:毎年2%以上の増加
- 最低賃金要件:事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上で維持
- 労働生産性の向上:年平均4%以上の向上計画の策定
特に重要なのは1と2の要件です。
給与支給総額には基本給、賞与、各種手当が含まれ、役員報酬も対象となります。
決算賞与や一時的な役員報酬でも要件を満たせますが、基本的には基本給のベースアップが望ましいとされています。
賃上げ要件が未達となった場合は補助金の返還が必要になりますが、全額ではなく未達率に応じた部分返還です。
例えば、10%の賃上げ目標に対して5%しか達成できなかった場合、補助金の半分を返還することになります。
ただし、業績不振や災害など特別な事情がある場合は返還が免除される可能性もあります。
売り上げが伸びていないようなケースや、大半が赤字だった場合は、賃上げができていなくても問題ない場合があります。
また、地震や戦争などの天災が起きて事業の継続が難しい場合も、賃上げができていなくても問題ないという制度になっています。
賃上げ要件はハードルに見えますが、従業員の増加や昇給計画と組み合わせれば十分に達成可能です。
むしろ、人材確保が困難な製造業では、計画的な賃上げは必要な投資とも言えます。
省力化投資補助金(一般型)の補助率と補助金額
省力化投資補助金の補助率と補助金額は事業者の規模によって異なります。
- 小規模事業者(製造業で従業員20人以下):補助率3分の2
- 中小企業:基本補助率2分の1、3000万円超の部分は3分の1
例えば、製造業の中小企業が6000万円の投資をする場合、
最初の3000万円に対して1500万円(2分の1)、残りの3000万円に対して1000万円(3分の1)、
合計2500万円の補助金が受けられる計算になります。
補助金の上限額は従業員数によって次のように設定されています。
- 5人以下:750万円
- 6〜20人:1000万円
- 21〜50人:1250万円
- 51〜100人:1500万円
- 101人以上:8000万円
さらに毎年6%以上の賃上げを行う「大幅賃上げ」の場合は、上限額が上乗せされます。
ただし、3年間で約20%の賃上げとなるため、リターンと負担のバランスを慎重に検討する必要があるでしょう。
省力化投資補助金(一般型)の申請から採択までのステップ
省力化投資補助金の申請から採択、そして補助金受給までの流れは次のとおり見込まれています。
- 申請準備:事業計画書の作成、必要書類の収集
- 申請書類提出:3月末締切
- 採択発表:6月上旬
- 交付申請:相見積書提出、事務局による確認(1〜2ヶ月程度)
- 発注・事業実施
- 納品・検収・支払い:2027年2月までに完了
- 実績報告書提出
- 補助金支給:最終的に2027年5月頃までに完了
申請書類では、投資による省力化効果を具体的な数値で示すことが重要です。
例えば「作業時間を30%削減」「不良率を5%改善」といった具体的な目標と、それを達成するための投資内容の関連性を明確に説明することが求められます。
また、交付申請以降の手続きも煩雑です。相見積もりの取得や事務局とのやり取り、実績報告書の作成など、細かな対応が必要になります。
初めて申請する場合は、申請経験のある支援機関や専門家のサポートを受けることで手続きの負担を軽減できます。
申請書作成では、専門用語を使いこなすよりも、投資の必要性と効果を誰が読んでも分かるように具体的に説明することが大切です。
特に自社の現状の課題と、補助金による投資でどう解決するかというストーリーが採択のポイントになります。
工作機械導入に活用できる補助金の実例
工作機械導入のイメージ
工作機械の導入で省力化補助金を活用するイメージとしては、以下のようなケースが考えられます。
測定機の導入
古い測定機では測定精度が悪く、手戻りが発生しているような場合、新たな測定機の導入により不良品の削減や工数削減が期待できます。測定プログラムを活用することで、さらなる効率化も可能です。
マシニングセンタとオプション機能
タッチプローブを備えたマシニングセンタの導入により、自動検査が可能になります。また、ガントリーやロボットを組み合わせることで、さらなる自動化が実現できます。
バイスチェンジャー付きマシニング
人が行っていた作業を機械に任せることで、作業効率の向上や人的ミスの削減が期待できます。
レーザー加工機とバリ取り機
複数の工程を集約することで、全体の効率化を図ることができます。
これらの導入は、生産性向上や品質向上につながるものであり、補助金の趣旨に合致する投資と言えるでしょう。
補助金申請の実務ポイントと注意点
採択率を高める申請書作成のコツと審査ポイント
補助金申請書の作成で採択率を高めるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
-
具体的な数値で効果を示す
単に「省エネになります」と書くのではなく、「年間電力使用量を23%削減」といった具体的な数値で表現することが重要です。審査では抽象的な表現よりも、明確な数字が評価されます。
-
現状の課題を明確に説明
「古い設備で生産性が低い」ではなく、「10年使用した旧式設備では加工精度のばらつきが大きく、不良率が5%に達している」といった具体的な問題点を示すことで、投資の必要性が伝わります。
-
投資内容と効果の因果関係を明確に
新設備のどの機能やシステムが、どのように課題解決につながるのかを論理的に説明できると、審査での評価が高まります。
-
実現可能性の高さをアピール
自社での過去の導入実績や、同業他社での成功事例などを引用すると説得力が増します。
多くの不採択案件に共通するのは、具体性の欠如です。
「効率化が図れる」ではなく「この機能により、この工程の時間が○○分短縮され、年間○○時間の工数削減になる」といった具体的な説明が求められます。
文章だけでなく、図表やデータを効果的に活用することも重要です。
ビフォーアフターの比較グラフや工程フロー図などは、文章だけでは伝わりにくい内容を視覚的に伝える手段として有効です。
審査では、投資の必要性と効果の具体性、実現可能性が重視されます。また、補助金の趣旨(省エネや省力化)に沿った内容であることも重要です。
補助金活用時によくある失敗と対策
補助金活用では思わぬ落とし穴があります。よくある失敗例と対策を紹介します。
-
スケジュール管理の甘さ
「申請しようと思ったら締切まで1ヵ月しかなかった」という事態は珍しくありません。
公募開始と同時に準備を始め、年間の補助金スケジュールをカレンダーに入れておくことが有効です。特に省エネ率の独自計算など、時間がかかる作業は早めに着手することが重要です。
-
要件の誤解
例えば「工場の空調も省エネになるから」と補助対象外の設備も含めた計画を立て、採択後に大幅な計画変更を余儀なくされるケースがあります。公募要領は細部まで確認し、不明点は事務局に問い合わせることが混乱を防ぎます。
-
過大な計画
「省エネ率60%達成」など実現困難な高い目標を設定すると、審査の際に計画全体の信頼性が疑われることがあります。達成可能な現実的な計画を立て、確実に実行できる内容にすることが採択への道につながります。
-
証拠書類の不備
設備導入後に「設置前の写真が必要」と気づいて慌てるケースも少なくありません。
採択後すぐに必要書類のリストを作成し、工事や導入の各段階で必要な証拠を収集することが大切です。
特に設置前・設置後の写真や廃棄証明書などは、後から用意できないものが多いため注意が必要です。
補助金申請は「言った通りにやる」ことが非常に重要です。
申請時の計画と異なる設備を導入したり、期限を守らなかったりすると、補助金が受け取れなくなるリスクがあります。
採択後の計画変更は原則として認められず、変更が必要な場合も事前承認が必須となるため、当初から実現可能な計画を立てることが成功の鍵です。
補助金受給後の義務と事後管理のポイント
補助金を受給した後にも、いくつかの重要な義務があります。
-
事業報告義務:一定期間(通常3〜5年)、事業の状況報告が必要です。この間の経営状況や設備の活用状況などを定期的に報告することになります。
-
財産処分制限:補助金で購入した設備には、一定期間(通常5年間)の処分制限があります。この期間内に売却や廃棄を行う場合は、事前に承認を受ける必要があり、場合によっては補助金の返還が求められることもあります。
-
賃上げ実績の報告:省力化投資補助金では、賃上げ計画に対する実績を毎年報告します。未達の場合は未達率に応じた補助金の一部返還が生じる可能性があるため、計画的な賃上げの実施と適切な記録管理が大切です。
- 台帳管理と現地確認:補助金で取得した財産の管理台帳を作成し、抜き打ち検査にも対応できるよう準備しておくことが必要です。設備には「補助金取得財産」である旨の表示も行います。
事後管理の負担を軽減するためには、交付決定時点でスケジュールと必要書類を整理し、担当者を明確にしておくことが効果的です。
特に人事異動などで担当者が変わっても対応できるよう、手順書やチェックリストを作成しておくと安心です。
まとめ
2025年度の省エネ補助金と省力化投資補助金は、製造業の設備投資を強力に後押しする制度です。
省エネ性能の高い設備への更新や、省力化・自動化による生産性向上を目指す企業にとって、これらの補助金は大きな味方となります。
申請にあたっては、各補助金の特性を理解し、要件に合った計画を立てることが重要です。
省エネ補助金では省エネ率の計算方法が、省力化投資補助金では賃上げ計画の実現性が採択のカギを握ります。
また、申請書作成においては、投資の必要性と効果を具体的な数値で示し、補助金の趣旨に沿った説明を心がけましょう。
スケジュール管理や必要書類の準備も計画的に進めることが成功への近道です。
私たち山善は、製造業における補助金の申請支援の実績が豊富にあります。
補助金を活用したい方、申請手続きにお悩みの方は、ぜひ私たちにお気軽にお問い合わせください。