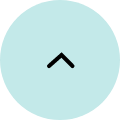【4月度 業界トピック】製造現場を変える最新技術と国際動向

今月は製造現場の生産性向上に直結する最新設備から、産学連携による次世代加工技術、さらには国際情勢が製造業に与える影響まで、幅広いテーマの記事が公開されています。現場の生産性向上や、変化への対応力を高めるためのヒントが見つかるかもしれません。ぜひご一読ください。
ピックアップ記事
ブラザー工業、工具100本搭載の30番MC
ブラザー工業から、主軸30番のマシニングセンタに100本の工具を搭載できる新しい機種が登場しました。これは、このクラスの小型工作機械としては初めての試みといいます。
多品種小ロット生産では、どうしても工具の段取り時間がネックになりがちですが、この100本マガジンならその時間を大幅に短縮できる可能性を秘めているのが大きな特徴です。
工具ストッカーが機械内に収まるため、設置場所を取らないのも導入しやすいポイントと言えるでしょう。
独自機構で高速な工具交換を実現しており、正面マガジンと左右ストッカー間の受け渡しは最短5秒。さらに、専用の工具管理アプリを使えば、直感的な操作やストッカーからマガジンへの一括移動も簡単に行えるようになっています。
この新しいマシニングセンタに対応したパレットチェンジャー「PC-1」も同時に発売されました。
最大40枚のパレットを収納でき、これによって夜間などの長時間運転も可能にします。
ワークや治具の形状を選ばずに搬送できるパレットクランプを採用しているため、ワークが変わるたびに治具の段取り替えをする手間が省け、ここでも段取り工数を削減できる点が魅力的です。
このマシニングセンタ2機種とパレットチェンジャーを組み合わせることで、同等の工具・パレット数を持つ他社製品と比較して、設置スペースが約半分に抑えられるというメリットも見逃せません。1台のパレットチェンジャーに2台のマシニングセンタを接続できる拡張性も備わっています。
産学が注視する「ロボット切削」
近年、多関節ロボットを使った切削加工が製造業で広がりを見せています。従来は欧州メーカー主導でしたが、安川電機やファナックなど国内メーカーがたわみ補正機能付き製品を開発したことで普及が加速。3月のセミナーでは実績と課題が報告されました。
ロボットSIerのトライエンジニアリングは10年間で46システムを納入し、建機部品や船舶スクリュー鋳型などの実績があります。最近は航空機CFRP部品の穴あけや建設現場での大型建材加工の相談が増加。これは工作機械では対応困難な大物加工や現場での柔軟対応が必要な領域でロボット切削が強みを発揮している証です。17メートル材加工や複数ロボットによる同時多軸加工など独自の利点も多くあります。
課題としては、広島大学の茨木教授の研究で示されたZ方向±0.1ミリの寸法誤差があります。これは重力やアーム姿勢の影響によるものですが、指令位置調整による精度向上も可能とされています。
イワタツールは課題解決のためスラスト荷重を抑えるヘリカル加工用エンドミルを開発中。「ロボットonロボット」といった新技術も探索され、切屑吸引などへの応用可能性が示唆されています。
自工会、トランプ関税「回避が当たり前」
日本自動車工業会(自工会)の片山正則会長が、米国の通商政策に関して記者会見でコメントを発表しました。
片山会長は、日本の自動車メーカーが1982年から米国での現地生産を進め、部品の現地調達を積極的に行ってきたことを強調しました。2023年までの累計投資額が616億ドル、年間生産台数が320万台、そして間接雇用を含め220万人もの雇用を創出しているといった具体的な貢献実績を示し、「これだけ貢献しているのだから、関税回避は当たり前のことだ」と語りました。
4月に入り、実際に一部で関税が発動した状況を踏まえ、片山会長はこの会見で、経済産業省など関係省庁と既に協議を開始していることも明らかにしています。
仮に関税の影響で国内生産の調整が必要になった場合、それは日本の自動車産業の競争力の中核であるサプライチェーン全体に影響を及ぼし、一度構造が変わってしまうと元に戻すのが非常に困難になるという懸念を示しました。
そのため、サプライヤーや国内の生産拠点に対する支援策についても検討を進めていることを示唆しました。
まとめ
今回ご紹介したMono Queの記事からは、製造業が直面する様々な課題と、それを解決するための技術開発や戦略が複合的に進んでいる様子が見て取れます。
新しいマシニングセンタによる多品種少量生産への対応力強化や、ロボット切削という新しい加工技術の可能性の探求は、まさに現場の生産性向上や自動化・省人化といった、私たち製造業の多くの皆様が共通して取り組んでいるテーマに直結する動きといえます。
一方で、自動車業界の関税問題は、グローバルなサプライチェーンの維持や国内産業の保護という、より大きな視点での課題を示しています。
こうした技術と経営、そして国際情勢が複雑に絡み合いながら、製造業の未来は形作られているのだということが改めて感じられます。
私たち山善では、製造業における最新動向や技術トレンドについて、メールマガジンを通じて定期的に情報を発信しています。