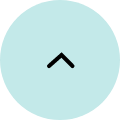【9月度 業界トピック】製造業最新動向まとめ~自動化・省人化と高難度加工で競争力強化~
今月は、「自動化・省人化」と「高難度加工への対応」という二つの大きな流れを感じさせる新製品のニュースが目立ちました。
特に、人手不足が深刻化する製造現場において、ロボットシステムが省スペース化と多品種生産への対応力を高めている点、また、半導体や電子部品に不可欠な難削材加工の安定性を飛躍的に向上させる工具 が登場している点が注目ポイントです。さらに、従来の工作機械市場とは一線を画した、より柔軟で手軽に導入できる加工機も本格展開が始まり、製造業全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる新たな選択肢が提示された月間といえます。
注目の3つの記事を、実務的な視点から解説します。
オーエスジー、セラ・ガラス用超硬ドリル
半導体製造装置や光学部品、電子部品の分野で、セラミックスやガラスといった特殊な素材の加工ニーズが高まっています。
これらの素材は非常に硬く脆いため、加工現場では工具寿命のバラつきや突発的な折損といったトラブルが、生産ラインの停止やコスト増の原因となっていました。
今回オーエスジーが発売したセラミックス・ガラス加工用超硬ドリル「DIA-MXD」は、この課題を解決する実践的な製品です。
耐摩耗性の高いHDGコーティングと、高い密着性を実現する新開発の超硬合金を組み合わせることで、従来の加工で頻繁に発生していたコーティング層の剥離を効果的に防ぎ工具寿命の安定化を実現しています。
この安定した耐久性により、工具交換頻度を減らし、生産効率の向上が期待できます。
具体的に期待できる効果としては、工具交換頻度の激減が挙げられます。例えば、炭素ケイ素(SiC)の直径0.1ミリという極めて小さな穴加工において、1本の工具で45穴以上を安定して加工できたという事例が報告されています。
これにより、機械の停止時間が大幅に削減され、総加工時間の短縮と生産コストの削減につながります。
高精度かつ安定した工具は、高難度部品の量産化を進める生産技術部門の管理職の皆様にとって、競争力強化に直結する大きなメリットとなります。
中村留精密工業、ロボ架台にストッカー内蔵の自動化システム
製造現場における自動化・省人化の推進は喫緊の課題ですが、特に多品種少量生産を行う現場では、ワーク(加工物)の変更に伴う段取り替えの負荷が大きく、自動化の壁となっていました。
また、ロボットセルを導入する際の設置スペースの確保も重要な検討事項です。
中村留精密工業が10月22日に発売する協働ロボットシステム「RoboSync TypeD」は、これらの課題に対し、非常に実践的なソリューションを提案しています。
この新仕様の最大の特徴は、ロボット架台そのものにワークストッカーと自動交換用ラックを一体化して内蔵している点です。
従来の仕様では架台とストッカーが分かれていましたが、一体化することでスペースを無駄なく使うことができ、現場の省スペース化に大きく貢献します。
さらに、ワークハンド爪、チャック爪、エンドエフェクタ類(ロボットの先端に取り付ける部品)を内蔵ラックに収納し、自動交換機能(オプション)を搭載することで、ワーク変更時の段取り替えを自動化することが可能です。
これは、多品種生産における機械の停止時間を最小限に抑え、稼働率と生産性の向上に直結する大きなメリットです。
操作はティーチングペンダントから簡単に行えるという点も、現場のオペレーターにとって親しみやすいポイントといえます。
また、同時に発売されたコンパクトな複合旋盤「NT-Flex+」は、R側主軸へのX軸追加や下タレットへのY軸追加により、3本の工具による同時加工(重畳加工)など、より複雑な加工パターンに対応しています。
これにより、長尺ワークの安定加工や複雑なミーリングが必要な部品をコンパクトな設備でこなせるようになり、高度な加工要求と省スペース化を両立したいお客様におすすめです。
津田駒工業、加工機販売を本格化
工作機械の導入は、通常、相応の設置スペースと大規模な電源設備を必要とし、初期投資も大きくなりがちです。
津田駒工業が本格販売を開始した小型加工機「TSUDAKOMA i-CUBE」は、周辺機器メーカーとしての同社が、既存の工作機械市場とは価格帯も用途も異なる新しい市場を開拓する戦略的な製品といえます。
この加工機がもたらす実務的なメリットは、まずその導入の柔軟性にあります。
100V電源で稼働し、キャスター移動も可能なため、一般的な工作機械が未導入だった溶接業者での肉盛り除去用途や、学術機関、開発部門での試作用途など、従来の工場設備に縛られない場所で活用が可能です。
特に、研究開発拠点や試作現場で積層造形(3Dプリンター)の隣に並べて仕上げ加工を行うといった新しい用途が想定されている点は、従来の工作機械とは異なる市場を開拓する戦略的な提案といえます。
また、加工初心者でも扱いやすいよう、タッチパネル式の簡易なUIや、3Dモデルを基にした加工プログラムの自動生成機能も搭載しているため、技術者の習熟度に依存しない運用が可能になります。重切削には向かないものの、アルミ、ステンレス、チタンの削り出しや穴あけ加工に対応できるため、試作や研究開発のスピードを上げたい部門には、定価580万円という価格帯も含めて、導入を検討する価値のある選択肢です。
同社は、傾斜円テーブルやATCといったオプションを拡張し、ロボットによるワーク交換を可能にすることで中量生産も視野に入れています。周辺機器(バイス・円テーブル)で培った技術力を活かし、医療や宝飾品といった新たなアプリケーションも準備しているとのことで、今後の製品ラインナップの拡張にも期待が高まります。
まとめ
製造業を取り巻く環境は、人手不足やコスト競争の激化、そして高精度・高難度な部品製造への要求増大といった課題に直面し続けています。
しかし、9月のニュースからは、これらの課題解決に直結する明確なトレンドが見えてきます。
まず、「複雑性と効率性の両立」が大きな潮流といえます。
中村留精密工業の例のように、複合旋盤はより複雑な加工パターンに対応しつつ、ロボットシステムは省スペース化と多品種対応を両立しています。そして、難削材加工における工具寿命の安定化は、生産の「見えないロス」を削減し、安定稼働と省人化の基盤を強化するという点で、製造現場の競争力強化の鍵を握るポイントです。
また、津田駒工業の事例は、工作機械のあり方自体が多様化し、導入の障壁が下がっていることを示しています。
100V電源や簡易操作、そして3Dプリンティング後の仕上げ加工といったニッチかつ成長性の高い領域を狙う動きは、私たち山善が提唱する「必要な時に、必要な場所で、必要な加工を行う」分散型モノづくりの展望を後押しするものです。
製造業の経営層・工場長の皆様には、既存の量産ラインだけでなく、開発部門や試作・補修の現場における「柔軟な自動化」の可能性について、改めてご検討いただくことをお勧めします。
私たち山善では、製造業における最新動向や技術トレンドについて、メールマガジンを通じて定期的に情報を発信しています。
ぜひ、弊社のメールマガジンにご登録いただき、より深い情報や特別なコンテンツをお受け取りください。