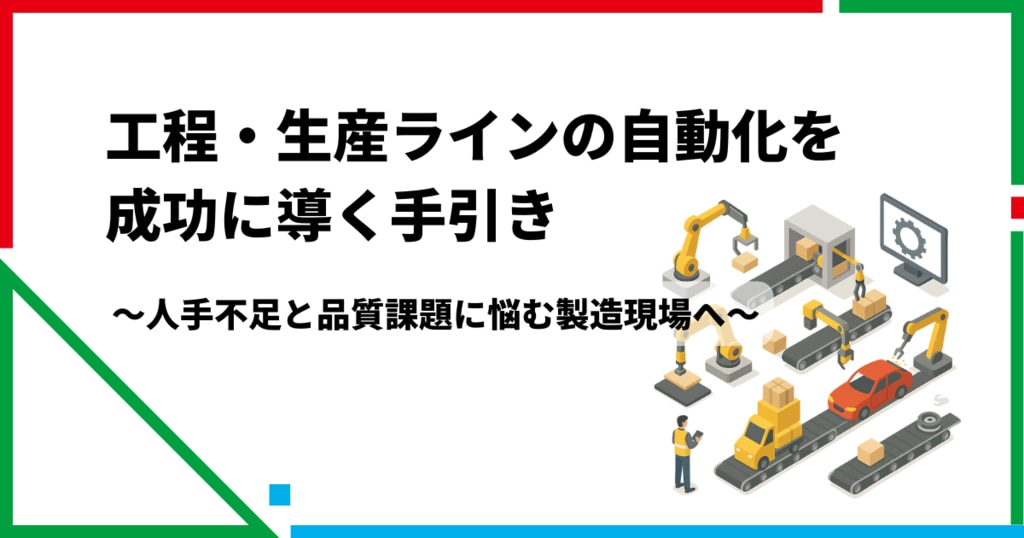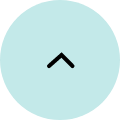ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの違いとは?製造現場で失敗しない20のチェックポイント
ファクトリーオートメーション(FA)やスマートファクトリー(SF)といった言葉を耳にする機会が増えてきました。
製造業の現場で「自動化」や「デジタル化」を推進するときによく出てくる言葉ですが、2つは似て非なるものです。混同してしまうと、自社にとって最適な投資判断を誤ってしまう可能性があります。
この記事では、ファクトリーオートメーションとスマートファクトリー、それぞれの意味や目的、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
「自社に必要なのはどちらか?」を判断できるよう、現場のよくある課題と解決の方向性、段階的な導入の考え方、また現場ですぐに使えるチェックリストをご紹介しています。
この記事の目次[非表示]
ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの違いと関係性
ファクトリーオートメーション (FA) とは?
ファクトリーオートメーションとは、工場における生産工程の自動化を指します。
主に各工程の設備主体の自動化がメインです。具体的には、人手に頼っていた作業を産業用ロボットや協働ロボット(コボット)、CAD/CAMで設計された部品を加工するNC工作機械、搬送装置、自動組立機、それらをコントロールする制御装置などに置き換えることで、生産効率の向上やコスト削減を目指す取り組みです。
たとえば、 半導体製造装置部品の製造を手掛けるF社様 においては、既存設備のパレット位置決め精度の問題が生産性向上の壁となっていました。
高精度と省スペースを両立した次世代マシニングを導入することにより、パレット位置決め精度が向上し、製品精度が安定化しています。またコンパクトな自動化システムの導入により、設備の入れ替えもスムーズ、かつ空いたスペースを活用して、新規設備の導入も実現しています。
このように、もっとも現場で課題になっているところから始められるのがファクトリーオートメーションの最大のメリットです。
導入メリット
1.生産性向上と品質安定化
定期的に人の手で行っていた設備管理や品質チェックなどの繰り返し作業を自動化することで、生産ラインの稼働率が向上し、人的ミスによる不良品発生などを抑制できます。
予知保全の取り組みとしては、センサーから収集されるリアルタイムデータに基づき、設備の予知保全、品質異常の早期発見と原因究明が可能になります。
2.人手削減とコスト抑制
人が行なっている単純作業や危険な作業が機械に置き換わることで、人手削減に繋がり、人件費の抑制につながります。
人手不足に悩む企業にとって、ファクトリーオートメーションは人材確保の課題解決にも貢献するはずです。
3.品質の均一化
ロボットや機械はプログラムされた通りに正確に作業を行います。
そのため人の経験やスキル、健康状態などによるバラつきがなくなり、製品品質の均一化ができます。これは、QCD(品質・コスト・納期)の改善に直結するポイントです。
4.危険作業からの解放
高温、高所、粉塵、重量物搬送など、危険が伴う作業を自動化することで、労働災害のリスクを低減し、現場で働くみなさんの安全を確保できます。
導入デメリット
1.初期投資が大きい
ファクトリーオートメーション実現のための自動化設備の導入には、ロボット本体やNC工作機械、制御装置、関連設備、システム構築費用など、多額の初期投資が必要です。
どの部分から自動化を行うか、補助金などが活用できるかなど、導入費用が回収できるかどうかの見極めが重要になります。
2.柔軟性に欠ける場合がある
特定の作業に特化してファクトリーオートメーション化を行った場合、製品の仕様変更や生産量の変動にスムーズに対応しにくい場合があります。
CAD/CAMデータとの連携や、汎用性の高い設備選定が求められるのはそのためです。
3.メンテナンスの専門性
自動化設備は高度な技術で構成されているため、専門知識を持った人材による定期的なメンテナンスが不可欠です。
社内での人材育成を進めたり、外部サポートを検討する必要が出てきます。
スマートファクトリー (SF) とは?
スマートファクトリーとは、IIoT(Industrial IoT:産業用IoT)、AI(人工知能)、ビッグデータなどのデジタル技術を最大限に活用し、工場全体の情報をリアルタイムで収集・分析・活用することです。
これにより、生産システムが自律的に最適化された工場を実現します。
ファクトリーオートメーションが個別の工程自動化に焦点を当てるのに対し、スマートファクトリーには工場全体の最適化と経営層の意思決定支援まで含まれています。また、個々の顧客ニーズに柔軟に応える「マスカスタマイゼーション(Mass Customization)」を支える仕組みとしても注目されています。
たとえば 金属加工になくてはならないツーリングシステムや治具などを手掛けるMSTコーポレーション様 では、ロボットシステムの導入からスタートし、無人搬送車やクーラントの自動供給など、これまで人が介在していたところを自動化・省人化を進めています。
さらに、加工状況をリアルタイムで集計したり、図面を見たり、加工前に過去のミスの事例を確認したり、と社員が工作機械に設置されたタブレットで情報を共有するスマートファクトリー化を進めていらっしゃいます。
導入メリット
1.生産性・品質の抜本的向上
ファクトリーオートメーションから一歩進めて、センサーから収集されるリアルタイムデータに基づき、AIによる生産計画の最適化、設備の予知保全、品質異常の早期発見と原因究明が可能になります。
これにより、生産性や品質を向上させることができます。
2.コストの最適化
エネルギー使用量の見える化と最適化、在庫の適正化、無駄な工程の排除などにより、工場運営にかかるトータルコストを削減できます。
製造実行システム(MES)や企業資源計画(ERP)システムとの連携により、より広範なコスト最適化が可能になります。
3.変化への柔軟な対応
市場や顧客ニーズの変化、予期せぬトラブルなどに対し、収集されたビッグデータをAIで分析することで迅速かつ柔軟に対応できます。多品種少量生産への対応力も高まり、マスカスタマイゼーションの実現に近づきます。
4.新たな価値創造
IIoTデバイスから収集・分析されたビッグデータは、製品開発やサービス改善、ビジネスモデル変革など、新たな価値創造の素です。製造業DX推進の第一歩につながります。
導入デメリット
1.導入コストが非常に大きい
スマートファクトリー化を一気に進めようとすると、IoTデバイス、各種センサー、データ収集・分析基盤(クラウドを含む)、AIシステム、ネットワークインフラなど、ファクトリーオートメーションを上回る大規模な投資が必要です。
2.高度な専門知識と人材
スマートファクトリーの導入・運用には、IT、データサイエンス、AI、セキュリティなど、多岐にわたる高度な専門知識を持つデジタル人材が不可欠です。
社内での育成は難しく、外部との連携を視野に入れる必要があります。
3.データ連携とセキュリティの複雑さ
「2.高度な専門知識と人材」と大きく関係しますが、工場内のあらゆる機器やシステムがネットワークで繋がり、大量のデータをやり取りするため、データ連携の複雑性やサイバーセキュリティ対策が非常に重要になります。
4.意思決定までに時間がかかり、また効果がすぐに出にくい場合がある
スマートファクトリーは工場全体の変革を伴うため、意思決定までに時間がかかることが多いです。また導入効果がすぐに出るわけではありません。
PDCAサイクルを回しながら改善していくと考え、中長期的な視点での取り組みが大切です。
ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの違い、製造業DXとの関係
ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの違いについて簡単に整理します。
一方で、製造業DXは、スマートファクトリーの概念をさらに広げたもので、工場だけでなく全社的な取り組みを指すことが多いです。
デジタル技術を活用して、製品・プロセス・ビジネスモデルを変革し、競争優位性を確立する取り組み全体を考えていきます。
製造業DXについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
製造業DXの事例を徹底解説 | 成功企業に学ぶ取り組みのポイントとは?
「自社に必要なのはどっち?」現場課題から導く判断ポイント
現場のよくある課題と選ぶべき方向性
製造現場では「どの工程から自動化すべきか?」「スマートファクトリーは本当に必要か?」といった疑問がよく挙がります。ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの違いを理解したところで、ここでは代表的な5つの課題とそれに対するそれぞれの適性について簡潔に整理します。
課題例1:特定の工程で人手不足が深刻化している・作業員の負担が大きい
特定の単純作業や繰り返し作業、または危険な作業が多く、熟練工の高齢化や若手人材の確保が難しい場合は、まずファクトリーオートメーションでの自動化が効果的です。
課題例2:製品の品質にバラつきがある・不良品率が高い
作業者の熟練度に左右される工程では、画像検査や自動組立など自動化の仕組み導入で標準化を図ることが有効です。さらに高度な品質管理にはスマートファクトリー化によるデータ分析の導入も検討を。
課題例3:生産計画通りに進まないことが多い・納期遅延が発生しやすい
リアルタイムで工程の進捗が見えない場合は、IIoTやMESによるスマートファクトリーの導入で全体最適が可能になります。
課題例4:エネルギーコストが高い・製造原価を削減したい
どこで無駄が発生しているかを見える化し改善につなげるには、スマートファクトリーによるモニタリングが効果的です。
課題例5:データが散在しており、経営判断に活用できていない
紙や別々のシステムに散在した情報は、スマートファクトリーによる一元管理と分析環境の構築によって、意思決定に活かせる基盤となります。
「まずはFA?いきなりSF?」ステップ導入の考え方
「自社の課題が見えてきたけれど、いきなりスマートファクトリー実現はハードルが高い…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。多くの場合、段階的な導入、いわゆる「スモールスタート」で検討・推進していく形をとっています。
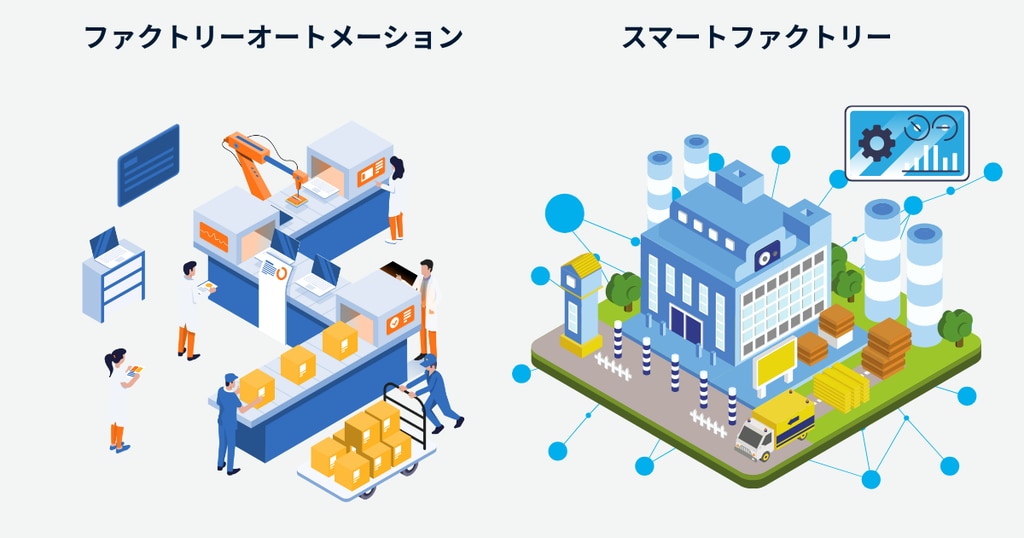
Step1:まずはファクトリーオートメーションから
まずは、特定の工程に絞ったファクトリーオートメーション(ロボット、画像検査、NC工作機械、搬送装置など)の導入から始めるのが一般的です。これにより作業の効率化や品質安定が実現し、比較的早く導入効果が実感できます。
Step2:ファクトリーオートメーションで得られたデータを活用し、部分的にスマートファクトリー化
次に、ファクトリーオートメーションで得られたデータをセンサーで収集し、稼働状況の「見える化」を進めていきます。部分的なIIoT化によって、現場の状態が把握できるようになり、スマートファクトリーの第一歩を踏み出せます。
Step3:段階的に工場全体の最適化へ
最終的には、複数の工程やシステムを連携させ、MESやERPといった上位システムとつなげることで、工場全体の最適化が可能になります。
このように、自社の課題とリソースに合わせて「スモールスタート→段階的拡張」を取ることが、無理のない進め方として多くの企業で採用されています。
もし、新規工場の建設が予定されている場合は、最初から最新のIoTデバイスやセンサー、ネットワークインフラを導入することができ、スマートファクトリーのコンセプトに合わせて、生産ラインのレイアウト、設備の配置、データ収集ポイントなど、データ連携しやすいシステムを設計できます。
もちろん初期投資の規模が大きくなりますので、投資対効果とどの範囲までスマートファクトリー化を行うかが難しいところです。
ファクトリーオートメーションとスマートファクトリー、どう進めるのか自社にとって効果的か、お気軽に私たちにご相談ください。
ファクトリーオートメーション or スマートファクトリー 導入適性診断チェックリスト
自社にとって、ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーのどちらが優先度が高いか、今考えるべきか、また適しているかを簡単にチェックできるリストを作成しました。
どのように推進していくかの参考に、ご活用ください。
※チェックリストを印刷してご覧いただくとより分かりやすいです。
チェックリスト
製造現場で感じる課題について
工場全体の情報活用と将来的な展望について
自動化に向けた現状や方針について
ファクトリーオートメーション or スマートファクトリー、自社で検討を優先するのはどっち?
自社において、ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーのどちらを優先的に検討すべきか、またどのように推進するのが適しているかがチェックリストからなんとなく見えてきます。
各質問への「YES」の数と以下の判断目安を参考にしてみてください。
「製造現場で感じる課題について」でYESが多い場合
現在、特定の生産工程における人手不足、品質のバラつき、作業の安全性といった喫緊の現場課題を抱えている可能性が高いです。
課題の箇所が明確な場合には、具体的な課題解決に直結するファクトリーオートメーションの導入から始めるのがおすすめです。ファクトリーオートメーションによる部分的な自動化は、比較的早期に効果を実感しやすく、コスト削減や品質安定化に貢献します。
特に質問1〜5へのYESが多い場合はファクトリーオートメーションの優先度が高く、質問6〜7へのYESがある場合は、スマートファクトリー化を部分的に取り入れていくことで解決が期待できます。
「工場全体の情報活用と将来的な展望について」でYESが多い場合
工場全体の生産性向上、情報活用による意思決定の迅速化、市場変化への柔軟な対応など、より広範なデジタル変革に関心が高くなっています。
スマートファクトリーの導入を本格的に検討する時期かもしれません。スマートファクトリーは大規模な投資や専門知識を求められますが、ファクトリーオートメーションによる自動化を基盤としつつ、データ収集・見える化から始めるなど、段階的な「スモールスタート」で進めていくのがおすすめです。
「製造現場で感じる課題について」「工場全体の情報活用と将来的な展望について」両方の質問でYESが多い、また判断に迷う場合
ファクトリーオートメーションとスマートファクトリーの両方のいいところどりをしながら解決できる課題を抱えている可能性があります。
まずファクトリーオートメーションによる部分的な自動化(例えば、特定のボトルネック工程へのロボット導入や画像検査装置の導入、予防保全、NC工作機械の導入など)から着手します。
これらの自動化導入で得られたデータや知見を活かしながら、少しずつ工場全体の情報連携やデータ分析(スマートファクトリー的な要素)へとステップアップしていく「段階的な導入」が、最も現実的かつリスクの低いアプローチです。
「自動化に向けた現状や方針について」でYESが多い場合
デジタル人材の不足、自動化・デジタル化への社内の抵抗、運用体制への懸念など、ファクトリーオートメーション/スマートファクトリー、いずれの導入においても、乗り越えるべき内部的なハードルが存在する可能性があります。
導入検討と並行して、これらの課題に対する対策(外部専門家との連携、社内啓蒙、段階的な運用計画の策定など)を具体的に進め、社内理解を得ることから先行して考えていくことが大切です。
ファクトリーオートメーションやスマートファクトリーの導入に関するご相談や、具体的なソリューションの提案をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
私たちは貴社の課題を理解し、ともに考え、無理のないファクトリーオートメーションやスマートファクトリーについて最適なプランをご提案いたします。
まずは「自社課題の見える化」から始めよう
ファクトリーオートメーション(FA)とスマートファクトリー(SF)は、どちらも製造業の生産性を高め、競争力を強化するための重要な手段です。
ファクトリーオートメーションは特定の工程の「自動化」に焦点を当て、スマートファクトリーは工場全体の「IoTによる情報連携とAIによる最適化」を通じて自律的な生産を目指す、より広範な概念です。
どちらを選ぶべきか、あるいはどのように導入を進めるべきか迷った際は、まず「自社の現状における具体的な課題は何なのか?」を明確にしましょう。
生産性、品質、コスト、納期(QCD)、人手不足など、さまざまな側面から課題を洗い出すことにより、ファクトリーオートメーションによる個別工程の改善が適しているのか、それともスマートファクトリーによる工場全体の抜本的な変革が必要なのかが見えてきます。
自社にとってどのように自動化を進めるのが最適なのか、「どこから始めれば?」というご相談が実は一番多いんです。まずは現場のお困りごとをざっくばらんにお聞かせください。